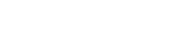第38回CINEX映画塾『山中静夫氏の尊厳死』上映&トークショー

第38回CINEX映画塾『山中静夫氏の尊厳死』上映&トークショーが8月1日、岐阜市柳ケ瀬商店街の岐阜CINEXと関市のシネックスマーゴで開催された。ゲストは岐阜県関市出身の村橋明郎監督。当初3月に開催予定だった本イベントだが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期となり、5ヶ月越しの開催。ゲストと観客席との距離を空けたり、座席の収容率を約30%にするなどの感染防止策を行った中、村橋監督が長年温めていたという作品の魅力や撮影秘話に迫った。(聞き手は後藤栄司岐阜新聞映画部長)

後藤:村橋監督とは映画部が始まる前になりますが、監督が自主製作で作られた『BANK』が渋谷の映画館で大ヒットして評判になった時に、監督が岐阜の関市出身だということを知りまして、会いにいきました。まだ映画部はありませんでしたが、この映画館で監督をお呼びしてトークショーを行ったというご縁があります。
村橋:監督をしました村橋です。今日は大変な時期に関わらず足を運んでいただいてありがとうございます。僕は神奈川に住んでおりまして、東京から来たわけではありません。4ヶ月以上、東京には足を踏み入れておりません。昨日車で来る時に、岐阜では非常事態宣言が出たので引き返そうと思ったんですが、来てよかったです。ありがとうございます。
後藤:この映画はシネスイッチ銀座では2月14日から公開が始まって、いい形でスタートされたので僕も楽しみにしておりましたが、自粛で上映延期ということになってしまいました。色々ご苦労はあったかと思いますが、作品を作るきっかけから教えていただけますか。
村橋:南木佳士さんという医者であり小説家である方の原作がありまして。出版されたのが26、7年前になるんですが、その頃に読んだんです。いつかこういう映画を撮りたいと、その当時から温めていた企画です。その頃に企画書を作っていろんなプロデューサーに見せたんですが、ほとんどのプロデューサーがこんな暗い作品はやりたくないという一言で終わってしまったんです。前作『ある取り調べ』の撮影が終わった後に再度原作を読み返したら、これは今こそやるべき作品だと思いまして。一気に自分で脚本にして、今回のプロデューサーに見せたら1週間後に返事が来ました。「実は自分もこういう映画がやりたいんだ」と。そこから話が進み始めました。
後藤:このところニュースでも安楽死問題、尊厳死に関わることが報道されていますが、そういった意味でもこの作品はタイムリーだと思います。原作の南木佳士さんは「ダイヤモンドダスト」で芥川賞をちょうど100回目で受賞されている方で。現在は長野県佐久市に住んでいらっしゃるんですね。
村橋:そうです。今でも非常勤で週に何回か病院で勤務されています。
後藤:今回の撮影も佐久市で撮られたんですよね?
村橋:一部鬼押出しで撮影していますが、ほとんどが佐久市での撮影です。
後藤:佐久市は医療がすごく進んでいる街だと伺いました。
村橋:そうなんです。関市と同じくらいの9万人ぐらいの人口なんですが大病院が3つあるんです。ドクターヘリが降りるような病院もあります。圧倒的に医療が進んでいます。
後藤:病院のシーンではその病院で撮影されたんですね。
村橋:中村梅雀さんの病室は病院じゃないんです。ロケハンで場所を探している時に唯一こだわったのが、病室の窓から浅間山がちゃんと見えることだったんです。見えれば病室でなくても会社の一室でもいいと言って探したんですけどなくて。佐久市の観光課の方も一緒に探してくださったんですけどいいところがなくて、最終的に観光課の職員さんから「市役所の8階の会議室を見てみますか?」と提案がありました。そこを見たら「ここだ!」と思いまして、そこだけ予算オーバーではあったんですけど会議室にセットを作りました。

後藤:撮影期間はどれくらいだったんですか?
村橋:実質12日間です。山などの実景撮影にはあとプラス2日間かかっています。
後藤:南木さんの原作を脚本にするにあたってどうアプローチされたんでしょうか。
村橋:原作は何回も読みました。原作をそのまま映画にすることはできませんから、何かを引いたり足したりする作業が必要なんです。自分で言うのはなんですが、その作業は上手く行っていると思います。脚本を褒めていただくことがあまりないんですけど(笑)
後藤:脚本は本当によく積み上げられているなと思います。そして、キャスティングもすばらしいと思います。中村梅雀さん、津田寛治さんというのは思った通りのキャスティングなんですか?
村橋:最初は医者が主役で患者はもう少し準主役的にキャスティングを考えていたんですが、ある時プロデューサーから「最近はダブル主演というのが流行っている。ダブル主演にしてこの2人はどうですか?」と提案があって。この2人ならいいかなと思いまして、それで決めました。
後藤:確かに、医者と患者ちょうど半々で分けられた脚本でダブル主演も納得です。実際に演出されるにしても、このおふたりなら凄い説得力を持って役に取り組まれたのではないかと思うんですが。
村橋:そうですね。脚本を読んで是非とも自分がやりたいと2人とも思ってくださって。津田寛治さんはこの作品のために13㎏減量しています。現場で初めて会った時に「大丈夫ですか?」と聞いたくらいです。中村梅雀さんも5㎏減量しています。梅雀さんには僕は衣装合わせの時に痩せなくてもいいと言ったんです。末期がんだとガリガリに痩せてボロボロになって死んでいくというイメージをするんですが、それは僕はやりたくなくて。ずっと最期まできれいで、最期に近づけば近づくほどきれいでいて欲しいと思って。逆に医者の方が疲弊していくという狙いがあったので梅雀さんにそう言ったんですが、梅雀さんは自主的に5㎏減量されていました。ふっくらしているからと5㎏痩せて現場に来たら津田さんは13㎏痩せていてびっくりという(笑)
後藤:梅雀さんと言えば映画だと『釣りバカ日誌』の秘書室長役とか、どの役を観ても絶対にいい人じゃないですか。これほど人柄が滲み出ているルックスの方はいないんじゃないかと思うんです。末期がんで佐久市で死にたいと自ら懇願するのもぴったりだなと思ったんです。佐久に浅間山と千曲川があるように、岐阜にも金華山があって長良川があります。僕は東京生活が長いので、晩年は故郷に戻りたいという気持ちがよく分かりますし、人が死ぬことに対してこんなに真面目に取り組んだ映画はなかなかないと思います。

■こんな医者がいてくれたらいいな
後藤:最近だと周防正行監督の『終の信託』だと安楽死と医療の問題があって。患者の安楽死に応えると殺人になってしまうという裁判ものもありましたし、黒澤明監督の『赤ひげ』でも扱われているテーマだとは思いますが、日本では家で死にたいと思っても、病院で医者と相談したとしても津田寛治さんみたいな医者はいないんじゃないかという現実に突き当たるんですけど、その辺りは監督もかなり考えられたのではないかと思うんですが。
村橋:そうですね。多分こんな医者はあんまりいないように思います。ただ、こんな医者がいてくれたらいいなと思って。南木さん自身がそういう医者だったのではないかと思います。南木さんご自身もうつ病になって何年も苦しんでいらっしゃいます。
後藤:南木さんご自身の自伝的な小説だったということなんですね。
村橋:そうだと思います。
後藤:南木さんとは色々お話しされたんですか?
村橋:公の場にあまり出られない方で、間に出版社の方が入ってくれてやりとりはしました。まず、脚本を書いた時に渡して読んでいただいて向こうから注文が来て。注文に対する回答を出してというやりとりをしていました。
後藤:原作と違うところはあるんですか?
村橋:原作に確実にないのは浅田美代子さん演じる初恋の人と会う件。それと、原作だと医者には息子が2人いて、そんなに深く関わっていない感じなんですが、映画では父と息子の話をやりたいなと思って設定を変えています。あとは台詞です。高野山の住職に知り合いがいまして。最初にできた脚本を読んでもらって。高野山の宿坊に泊まって住職にいろんな話を聞いたんですが、それが原作にない台詞として反映されています。例えば「人間はその人が生きていたようにしか死ねない」とかです。この台詞は津田寛治さんに言わせようと。

後藤:監督らしいユーモラスなシーンもありますよね?梅雀さんが看護婦さんのお尻を触るシーンとか。生と死を見つめた作品の中でふっと息を抜いたようなシーンがあるのがいいです。
村橋:袋綴じの話のシーンもそうです。原作にはないです。怒られるかなと思ったんですが喜んでいただけたようです。
後藤:津田寛治さんが辞世の句に対して夜自転車を走らせて夜だから見えないと言っていたりとか。
村橋:ああいうのを自分で書きながら思うのは「この台詞、津田さんはちゃんと言ってくれるかなあ」ということなんです。役者の方から時々「この台詞は言いにくい、言いたくない」と言われることがあるんです。そんなこともあり、津田さんに撮影の時に聞いたら「これいいじゃないですか」と本人がのってくださったので撮りました。
後藤:撮影もすばらしいです。撮影監督は髙間賢治さん。重鎮の撮影監督さんですが、その辺りのコンビネーションはどうでしたか?
村橋:70歳を越えている大ベテランの撮影監督ですが、すごく柔軟でちょっとせっかちなところもあって撮影は早いです。そんなに打ち合わせをしなくても分かり合えるというところはありました。本当に現場はスムーズでサクサク撮りました。
後藤:主題歌は小椋佳さんですが、これは監督から要望されたんですか?
村橋:僕からプロデューサーに相談したところ、プロデューサーが小椋さんの事務所と繋がりがあったのでオファーしてもらいました。向こうからも「映画のために作りましょうか?」と提案していただけて、こっちは予算があまりなかったので大丈夫かなと思ったんですが、ちゃんと作っていただけました。
■大学受験の失敗が映画と出会わせてくれた
後藤:村橋監督もメジャーで撮ったり、自主製作で自分の企画を持ち込んで映画製作されていますよね。その辺りの現実は今どうなっていますか?
村橋:今までも結構きつかったんですが、特に僕みたいなポジションでいると自分の撮りたいものは自分で作るしかないんです。向こうからオファーが来ることがあまりないので。そういう人間が必死になって作っているんですが。新型コロナウイルスの影響でこれからどういう映画作りになっていくか全く見えない状況です。この映画が大ヒットしてアカデミー賞を獲るくらいになったら黙っていても仕事が来るのでいいとは思うんですが。本当にどうしましょうという感じです。
後藤:監督のスタンスの素晴らしいところは、数年経つとまた次の映画の準備をされていることなんです。本当に立派だなと思います。監督はそもそも、なぜ映画の道に進もうとされたんですか?
村橋:大学受験に失敗しまして、名古屋の予備校に行くことになったんです。通うこともできたんですが、親が下宿させてやるから一生懸命勉強しろと言って河合塾から5分くらいのところで下宿しました。その間に映画を観るようになって。1973年のアメリカ映画『スケアクロウ』を観て、「なんだこれは!こんな世界があるのか」と。それまでは映画に興味はなかったんですけど、大学の受験雑誌を見たら芸術学部映画学科というのを見つけて。ここいくしかないと思って日大へ進みました。総合学科なので教職だけ取っておけば良かったんですが、遊びたかったのでそれも取らず(笑)
後藤:大学に入ったとはいえ、そんな簡単に映画監督にはなれるわけはないですよね?
村橋:いばらの道ですね。まず、あの頃は助監督になれなかったですね。大学を卒業して3年ぐらい色々アルバイトをしながら、コツコツ脚本を書いて「助監督になりたいんだ」と回って。
後藤:監督がここを見てほしいというところはありますか?
村橋:実はタイトルなんですが、僕は尊厳死という言葉を使いたくなくて。題名を変えたいと何回か頑張ってみたんですが、南木さんが原作のタイトルのままで使ってほしいと要望があって。尊厳死とはなっていますが、尊厳死とは何ぞやというのを追求しているのではなく、どういう風に人が死んでいったかという話ではなくて、限りある時間をどう生きたか、それに医者がどう向き合ってくれたかという作品だと自分では思っていますので、その辺りがうまく繋がればいいなと思います。梅雀さんが完成した作品を初めて試写で観た時に「もうちょっと自分も一生懸命生きていこうと思った」と言われて。それが一番嬉しい言葉でした。
■質疑応答
観客:先ほど脚本について原作者から注文があったと言われていましたが、結構直されたんでしょうか?また、監督としては医者と患者どちらの方に思いを置かれていますか?
村橋:感情移入ということで言えば、医者と患者どちらにも五分五分です。どちらもしっかり描きたくて。二人というよりも二つの家族ですね。その辺がうまく出ればいいなと思いました。脚本の縛りについては南木さんと直接話はしていないんですけど、結構細かい指摘をされたんですが、それはご本人の意見もありますが間に入った出版社の意見でもあったと思います。それに対して30項目ぐらいあったと思いますが、一つひとつこういう思いで変更したとか追加しているとかを書いて、それを送り返したら「もう言うことはない」と言われました。出版社から「こんなきちんと回答してくれる監督は初めてです」と言われました。完成試写を五反田でやった時に南木さんがご夫婦で来てくださって、映画を観て原作者が何を言うんだろうというのが心配だったんですが、観終わって南木さんからこちらに近づいて来て「とてもいい映画でした」と声をかけてくださったのでホッとしましたね。
文:涼夏
岐阜市生まれ岐阜市育ち。司会や歌、少し芝居経験も。テレビや映画が大好きでラジオでの映画紹介、舞台挨拶の司会も始める。岐阜発エンタメサイト「Cafe Mirage( http://cafemirage.net/ )」で映画紹介、イベントレポート執筆中。