
国家の闇をハードに描写していくジャーナリズム映画
2020年11月13日
赤い闇 スターリンの冷たい大地で
©FILM PRODUKCJA - PARKHURST - KINOROB - JONES BOY FILM - KRAKOW FESTIVAL OFFICE - STUDIO PRODUKCYJNE ORKA - KINO ŚWIAT - SILESIA FILM INSTITUTE IN KATOWICE
【出演】ジェームズ・ノートン、ヴァネッサ・カービー、ピーター・サースガード、ジョゼフ・マウル
【監督】アグニェシュカ・ホランド
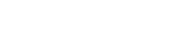












何が起きてもおかしくない不安感で、一瞬たりともスクリーンから目が離せない
史実を基にした映画は数知れず。しかし、史実の映画化は諸刃の剣だ。衝撃の内容を上手く描くことで傑作となるか、事実に足を引っ張られ駄作となるか。さて、本作はどちらだろうか。そんな思いで見始めた本作は前者であったので、非常に面白かった。
舞台は1930年代、大恐慌が全世界に広がっていた時代。なぜかソ連だけが潤っていることに疑問を持ったジャーナリスト、ガレス・ジョーンズ(ジェームズ・ノートン)はヒトラーへのインタビューを成功させた経験からスターリンのへのインタビューを行うべく、単身モスクワに乗り込む。映画は序盤、彼の旧友が謎の死を遂げるところから始まる。彼の行く先を暗示させるような冒頭である。
本作でまず驚かされるのは、ジョーンズのジャーナリスト魂である。妨害に遭えば遭うほど、真実への執着は強くなっていく。国家が真実を隠すのならば、それをどこまでも追求していく姿勢にジャーナリズムの本質を感じずにはいられない。後半、ジョーンズは国家による虐殺に等しい意図的な飢饉を目の当たりにする。そこに広がっていたのはあまりにも悲惨な現実である。恐慌の中、唯一潤っているソ連の嘘とカラクリがそこにあった。そして、その描き方にさらなる衝撃を受けた。とことんまでハードに描写していくのだ。雪景色の冷たさ、道に転がる遺体、人肉食までしっかり画にしていく。ジャーナリズムが機能しなくなった国が迎える1つの成れの果て。旧知のジャーナリストも逮捕され、その国でジャーナリストとして生きていくためには体制側に転向するしか道はないのだ。
そんな現代への強烈なメッセージを放ちながら、映画は一切の緊迫感を失うことなく展開していく。ソ連というどこに居ても安心できない国で単身行動しているジェームズ。次の瞬間に何が起きてもおかしくない不安感が全編を覆う。だからこそ、一瞬たりともスクリーンから目が離せない。
真実か、自分の命か。そんな究極の選択を迫られたジャーナリストの理想を、映画館で感じてみてはいかがだろうか。
語り手:天野 雄喜
中学2年の冬、昔のB級映画を観たことがきっかけで日本映画の虜となり、現在では24時間映画のことを考えながら過ごしています。今も日本映画鑑賞が主ですが外国映画も多少は鑑賞しています。
語り手:天野 雄喜
中学2年の冬、昔のB級映画を観たことがきっかけで日本映画の虜となり、現在では24時間映画のことを考えながら過ごしています。今も日本映画鑑賞が主ですが外国映画も多少は鑑賞しています。